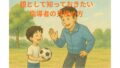子どもの「余計な行動」には意味がある
子どもは年代に応じていろいろな行動をします。
赤ちゃんの時にはいろいろな物を口に入れます👶
幼児期にはいろいろな場所に登ったり、物を触ったり、投げたりします👧
小学生になると、鬼ごっこやドッジボールなどをして何時間でも遊んでいます👦
それを見て、
「何でそんなに余計なことをするの!」と、イライラすることもあるかもしれません💦
大人から見ると、子どもは一見無駄なことをしているように見えることがあります。
でもこの記事を読めば、
それらが感覚刺激を求めて脳を発達させている大事な行動だと分かります。
一見無駄に見えることの中にこそ、
子どもの発達にとってとても大事な要素が詰まっているのです。
感覚刺激を求める子どもの行動

生まれたばかりの赤ちゃんを観察していると、改めてこう感じます。
「子どもはその時に必要な感覚刺激を求め、運動によって脳を発達させているのだ」 🧠
赤ちゃんは柔らかい物に触れたり、くるくる回るものを見たりするのが好きです。
幼い子どもも同じで、その時に必要な感覚を求めます。
2〜3歳ごろには何でもかんでも触ったり、(触ってほしくないものほど触る😅)
何回も「高い高い」を要求したりします。
✅これは皮膚感覚や平衡感覚に刺激を求めているということです💡
この時期、ブランコや滑り台、シーソーなどを好みますが、それらも平衡感覚を刺激する遊びだからなのですね!
小学生になる頃には、求める刺激がまた変わります。
男の子はオニごっこなど空間認知が必要な遊びに熱中し、
女の子は縄跳びなどリズム感を使う運動を好む傾向があります。
脳の発達の仕方が男女で違うことが分かってきており、その影響といわれています。
女の子の方がリズム能力は早く発達するそうで、確かにスキップは女の子が早くできますよね。
一方、男の子は空間認知が早く発達するので、ボールゲームが得意なのです。
高学年になれば、もっと知的な戦略や戦術が必要なスポーツ(野球・サッカー・バスケットなど)を好むようになります⚽️
また、スポーツに限らず、音楽や絵画に夢中になるのも感覚刺激を求めての行動といえるでしょう♬
「じっとしていなさい」は脳の発達を止める?

このように、適した時期に適切な感覚刺激を得ることで、脳は発達していきます🧠
ですから、
「子どもに、汚いから、危ないからじっとしていなさい!」
というのは、
「脳を発達させるのをやめなさい!」と言っているのと同じことです😵
運動指導によっても、子どもたちの脳を発達させることができるのです!
無駄を省きすぎる教育の落とし穴
しかし今の社会を見渡すと、情報化社会の影響もあり、
幼いうちから特定のことだけを早くできるようにさせようとする場面が多くあります。
例えば、
✅余計なことを省いて専門的な運動種目だけに専念させる
✅早期教育として塾通いをさせる
といったことです。
確かに、無駄を省いて同じことを繰り返せば早くできるようになるため、
一見「上達した」ように見えます。
しかし、それは決められたことしかできないように固定化してしまい、
本来求めたい柔軟な動きとは逆方向なのです。
これは、雛が試行錯誤して自分で殻を破ろうとしているのに、
大人が「早く出てこい!」と外から割ってしまうようなもの🐣
待つ心を持つ大人へ

私たち大人から見ると「余計」に見えることを子どもがしている時、
その姿をもっと大きな視点で待つ心を持つことが大切なのではないでしょうか。
これは運動指導に限らず、家庭教育・学校教育・社会教育すべてに当てはまります。
私は子どもが運動を通して自らの身体を探り、
主体的に学んでいく「科学者の姿勢」を身につけてほしいという願いを込めて指導をしています😊
そしてその学びが、スポーツだけでなく勉強や芸術など人生のあらゆる場面に応用できるようになることを願っています。
「運動指導は子育てと一緒だな」と改めて思います。
まとめ
✅子どもはその時に必要な感覚刺激を求めている
✅その刺激によって脳は発達していく
✅大人はそのことを認識し、待つ心を持って見守ろう
一度深呼吸をして、子どもの成長を急かしていないかを振り返ってみましょう😊
この待つ時間が、子どもの未来への教育投資となるのです。