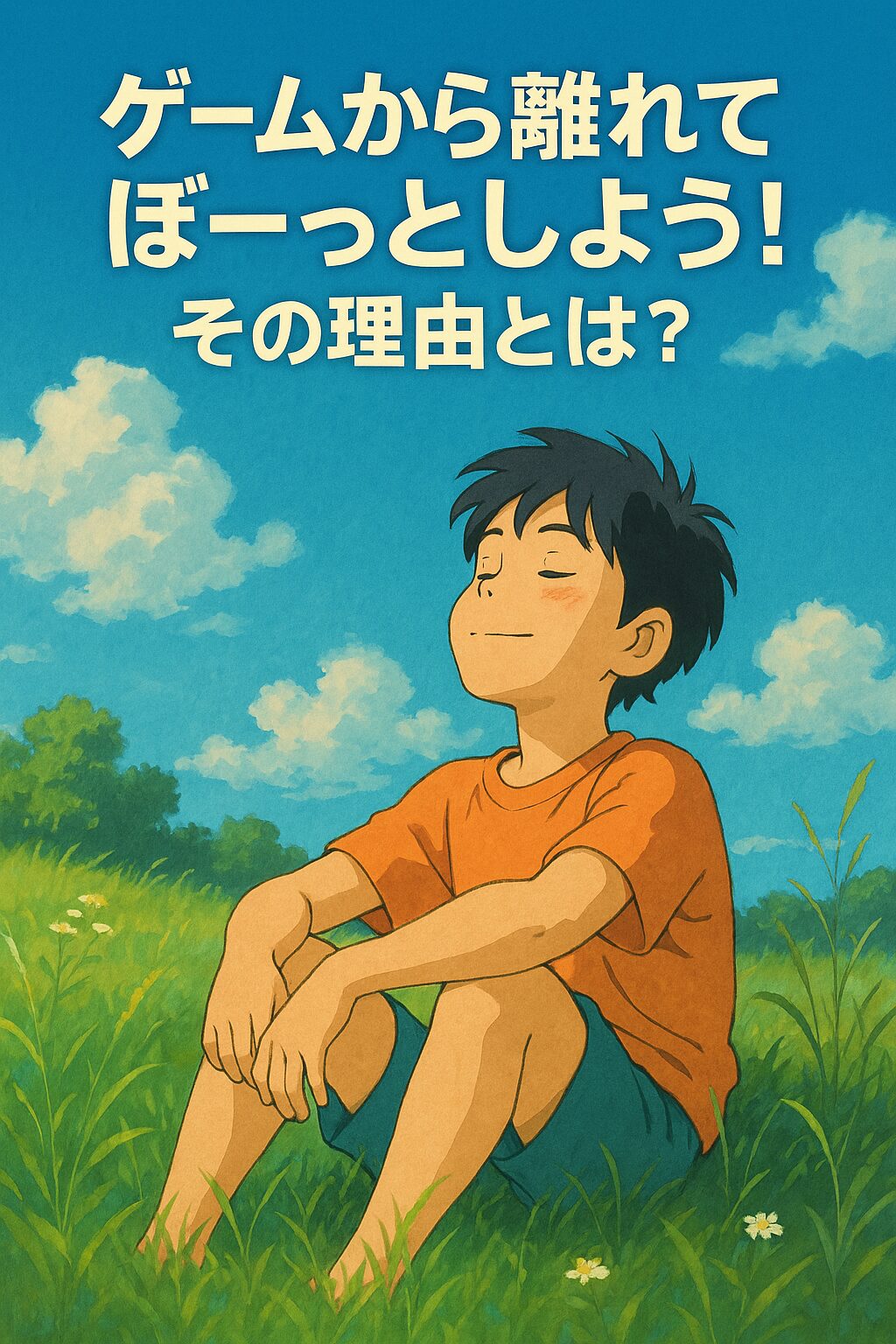「ゲームばかりしている子どもを見て、ちょっと心配…でも、どう声をかけたらいいか分からない。」
そんなふうに感じている方へ。実は“身体を使うこと”が、子どもの「知性」を育てるうえでとても大切なんです。
この記事では、運動指導の現場から見えてきた子どもたちの変化や、ぼーっとする時間の大切さについて、脳科学の視点からもお伝えします。
夏休み、ゲームから少し離れて“感じる力”を育てるヒントを見つけてみませんか
子どもがゲームばかりで、親の心はもやもや

夏休み。
暑い日が続くと、外に出て身体を動かすのがつい億劫になってしまいがちです。
子どもたちが涼しい部屋でゲームをして過ごしたくなる気持ちも、分からなくはありません。
でも、親としてはゲームばかりしている様子が気になるもの。
そのことを注意すると、
「なんでゲームしちゃダメなの?」
と聞かれて答えに詰まることもあるかもしれません。
そんな時には、「身体を使わないと頭が良くならないから!」と伝えてみてください。
“体感”が子どもの感性を育てる

公園でお子さんと一緒に身体を使って遊んでいると、自分が子どもだった頃の“体感”が鮮明に蘇ってくることはありませんか?
全力でブランコを漕いだ時のゾワゾワする浮遊感、
友達とつながって滑り台をすべった時の肌の温かい感触、
裸足で泥遊びをした時のぬるりとした感覚……。
そんな時、身体には心臓がドキドキしたり、汗をかいたり、鳥肌が立ったりといった反応が起こります。
こうした“体感(体で感じること)”を通じた身体の反応によって、感動や興奮、心の揺さぶりが生まれ、
その結果“感性”が育まれるといわれています。
体感の不足が生む、他者への想像力の低下

私は普段、各地の学校や園で運動指導を行っており、たくさんの子どもたちと接する機会があります。
コロナ以降の子どもたちの変化の中で、気になることの一つに、
相手の気持ちを想像するのが苦手な子が増えているという点があります。
たとえば、
- 友達を強く叩いてしまう
- 相手との距離が近いのにボールを思い切り投げてしまう
その背景には、“体感”の不足があるように思います。
体感があることで、私たちは相手の気持ちをわが事のように理解することができます。
しかし、今の子どもたちはオンラインゲームや動画での“体験”は多い一方、
リアルな世界での「体感」が圧倒的に不足しているのです。
ゲームのやりすぎは脳に「運動した気」を与える

今のゲームは非常にリアルで、キャラクターを操作していると、まるで自分が実際に走ったり跳ねたりしているような感覚になります。
その結果、脳が実際に運動したと錯覚してしまうのです。
これは、お腹が空いた時にお菓子を食べて、満腹になったように錯覚するのと似ています。
「ご飯の前にお菓子を食べたらダメ!」と叱られた経験、ありませんか?
ゲームのやりすぎによって、現実世界でのリアルな体験を奪われてしまう危険性があるのです。
知性を育てるのは“身体を使うこと”
ここ数年でAI(人工知能)の進化が目覚ましく、社会を大きく変えています。
AIが持つのは、インターネット上の情報から得た「知能」。
一方、人間が持つ「知性」は、自分自身の身体での経験から生まれるものといわれています。
京都大学の明和政子先生によると、 脳にはON状態とOFF状態があり、
ON状態は“集中ネットワーク”といって意識化、言語化や計画・実行している時の状態。
たとえば集中して考えている時や勉強して記憶している時などの状態です。
OFF状態は“ぼーっとネットワーク”といって、その名の通りぼーっとしている時や、何かに没頭している状態。
たとえば、シャワーを浴びている時、楽器演奏、雑巾がけなどに没頭している時がOFFの状態です。
実はこの“ぼーっとしている時”・“没頭している時”のOFF状態で、神経回路がつながり「ひらめき」が生まれることが分かっていて、これこそが創造的知性の根幹といわれています。
ニュートンがりんごが木から落ちるのをぼーっと見ていて万有引力を発見した、という話にも通じますね。
ONとOFFの切り替えを担っているのが、“気づきネットワーク”と呼ばれる、自分の内側に意識を向ける時に働く脳の機能です。 これはジョギングや泥遊びなど、身体を通した体験によって活性化されます。
つまり、子どもたちの「知性」の土台をつくるのは、身体を使ったリアルな体験なのです。
(参考:明和政子『ヒトの発達の謎を解く』)
“ぼーっとする時間”こそ、知性の源泉

こうした知識をもって、AIが広がり“コスパ・タイパ”が求められる今の社会を見渡すと、
子どもたちがゲームやスマホなど外部からの情報にさらされすぎて、
“ぼーっとする時間”や“自分の内側に意識を向ける時間”がどれくらいあるのか、と心配になります。
風の音を聞いたり、木漏れ日を見たり、虫を眺めたり。
そんな何気ない“間”が、子どもたちの知性を育てる豊かな時間なのです。
そんな認識が広がれば、ゲームやスマホを置いて自然の中に子どもを連れ出し、
ぼーっとしている子どもたちを大らかに見守り、待つことができるようになるのではないでしょうか。
【まとめ】身体を使い、ぼーっとする。それが未来を育てる

このような理由から、身体を使うこと・ぼーっとすることは、知性を育むうえでとても大切です。
AIにはできない、深くて豊かな知性は、“動いて・感じて・内省する”時間の中に育っていきます。
子どもたちの創造的知性を育むためにも、
この夏休みは、ぜひゲームやスマホから一歩離れて、
親子で自然の中に出かけ、“身体を動かして、ぼーっとする時間”を過ごしてみてください。