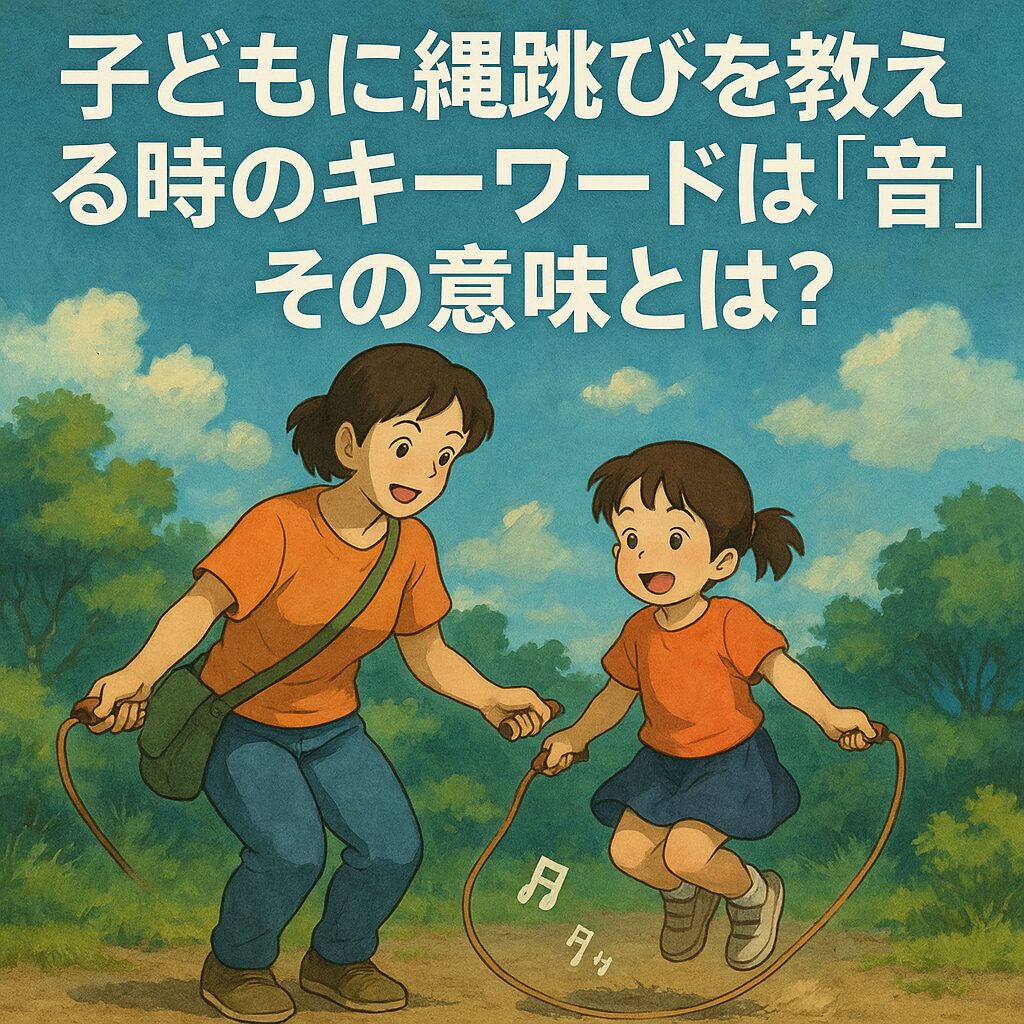縄跳びはジャンプという負荷が高い動きを続けるので運動量が多く、子どもが体力をつけるのにとてもいい運動です。
でも…
「できない!」「難しいから嫌い!」
せっかく教えようとした時に、そのように言われて困った経験はありませんか?
親としてはなんとかできるようにしてあげたい。
でも教え方が分からない。
とりあえず気合で頑張らせるしかない!
でも結局全然できず、お互いにイライラしてしまう…。
そんな時には、まず「音」に注目させましょう。
縄跳びの指導では、この「音」がキーワードになります!
この記事では、子どもに縄跳びを教えるときに意識したい「音」に着目したオススメの方法をご紹介します。
子どもにとって縄跳びはなぜ難しいの?

自分が子どもの頃を思い出してみてください。
縄跳びは得意でしたか?苦手でしたか?
得意だった方は、特に何も意識しなくても最初からピョンピョン跳べたと思います。
苦手だった方は、何が難しかったか覚えていますか?
縄を手で回すこと?足でジャンプすること?全身のリズム?
実はそれらを総合的に組み合わせるのが難しかったのです。
手足を協応させるのが大変
縄跳びの際に重要なのは、手で縄を操作しながらタイミングよく足でジャンプをするという「手足の協応能力」。
これは幼い子どもにとって、非常に複雑な運動です。
それをリズムよく続けることは、さらに難易度がさらに高くなります。
縄跳びは運動能力を高めるためにとても良い運動ですが、縄という道具を自分の思うように操作できずに、イライラして嫌いになってしまう子もいます。
跳ぶ時には手を上に上げる

しかも人間はジャンプをする時に、自然と下から上に手を振り上げます。
(立ち幅とびやバレーボールのスパイクをする時のことを思い出してみてください)
「前まわし跳び」はそれとは逆の動きとなり、縄跳び初心者にとっては難しく感じることがあります。
初めて縄跳びをする時に、後ろ回しで縄を回す子がいるのは、こうした理由があるのですね。
前回し跳びよりも先に、後ろ回し跳びができるようになる子もいます。
そのような場合は、無理に直さず、自由にさせてあげるほうが良いでしょう。
まずはリズムよく跳ぶという能力を育てることが目的。
自由に動く中で自然と学習能力が高まり、のちに前回し跳びもスムーズにできるようになります。
縄跳びを教える時のキーワードは「音」!

実際に縄跳びを教えるときに大切なこと、それは「音」です。
以下のような4つのステップを意識してみてください。
指導の際の4ステップ
- 縄を半分にたたんで片手で回す。
「縄で床の太鼓を叩いて音を出してみよう」 - 半分にたたんだ縄を片手で回しながら、歩いたり走ったりして移動する。
「リズムよく音を出してみよう」 - 両手で縄を持ち、その場で前回し跳びを行う。
「自分の前の床の太鼓を叩いて、その音を跳び越してみよう」 - 縄を回す強さを意識させる。
「大きな音ではなく、やさしい音をつくってみよう」
課題の設定が重要
一般的には、まずは縄の持ち方や構え方を教えたり、手首の使い方や腕の動かし方などの型を教えることが多いと思います。
でも、そうした運動の「型」は後で十分。
まずは「音をつくる」という課題を設定してあげることが大切です。
運動の順序性を理解する

様々な運動ができるようになるには順序性があり、
子どもに運動を教えるときはその順序に沿って進めるのが効果的です。
その順序性で分かりやすいのは、
身体の「中心から末梢へ」「上から下へ」「同側から対側へ」といった流れです。
そう考えると、体の外側にある手首を使って縄を回すのは高度な動きです。
さらに腕をクロスして行う「あや跳び」や「交差跳び」は、非常に難易度の高い運動です。
思ったような跳び方がうまくできずに苦手意識を持ってしまう子もいますが、
本来の目的は、その運動をやろうとすることによってリズムの能力や用具を操作する能力を育てること。
さまざまな跳び方ができるのは「現象」であり、
**それを通して運動能力を刺激・向上させるのが「本質」**です。
遊び心を忘れずに
そもそも縄跳びは「遊び」。
私たち大人も、心に“あそび”を持ちながら、子どもたちが遊ぶ姿をあたたかく見守りたいものですね。
まとめ
子どもに縄跳びを教える時に意識したい順番や声かけについて書いてきました。
キーワードは「音」。
このポイントを意識して、お子さんと一緒に縄跳びを楽しんでみてください。
縄跳びは運動量が多いので、大人の体力づくりにもオススメですよ😊