陸上競技400mハードル日本代表として三度オリンピックに出場し、
「走る哲学者」と呼ばれる為末大さん🏃♂️
今回は、そんな為末さんの著書『熟達論』をご紹介します。
この本では、
「何かができるようになり、できるようになることで自分自身が変化する──これが熟達のプロセス」と説明されています。
スポーツはもちろん、音楽や芸術などにも通じる内容で、
子どもがどのように物事を上達させるのかを知りたい方におすすめです😊
物事を学習し熟達していく5つの段階

為末さんによると、熟達のプロセスには以下の5つの段階があります。
- 遊
- 型
- 観
- 心
- 空
すべては**「遊び」から始まり**、
無意識に基本的な動きができる**「型」**を身につけ、
「観察」によって関係や構造を理解し、
無意識で「中心」を捉えられるようになることで自在に動けるようになり、
やがて「空」──いわゆる“ZONE(ゾーン)”の境地に至るそうです☝️
第一段階が「遊び」である理由
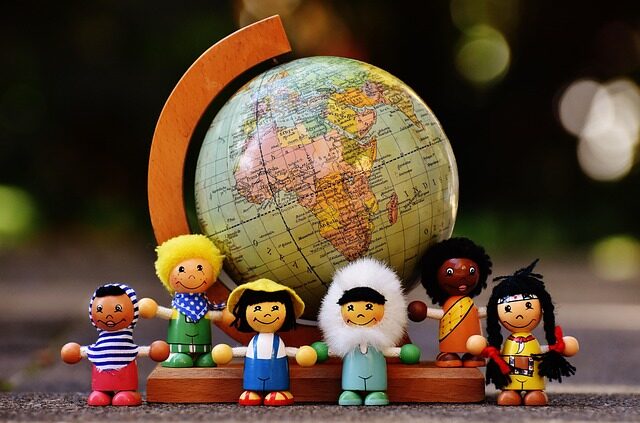
最初に「遊び」があるという点に、私も深く共感しました。
確かに、オリンピック選手も将棋の名人も、**最初は「面白いから始めた」**のです。
その面白さが探求を続ける原動力となり、やがて熟達への道につながります。
「型」から始める弊害

逆に「遊」を飛ばしていきなり「型」から入ると、
途中で探求が止まり、壁にぶつかってしまう危険があります💦
「面白いからやる」「やりたいからやる」
この段階を経ることが、その後の成長を大きく左右します。
この考え方を知れば、子どもが何時間も夢中で遊んでいる姿を、
もっと温かく見守れるかもしれません😊
子ども時代に大切なこと

模索するようにたくさん遊ぶ
為末さんの講演で心に残ったのが、小学生時代のエピソードです。
当時所属していた陸上クラブでは、週2日の練習のうち、
1日は陸上の練習、もう1日は遊びだったそうです。
「探索するようにたくさん遊んでおくと、その時は無用と思ってもいつか有用になる。子ども時代に上を狙いに行く指導者に出会わなかったのが最大の宝物だった。」
この言葉には深い意味が込められています👀
身体と環境の間で遊ぶこと
為末さんはスポーツを**「身体と環境の間で遊ぶこと」**と定義しています。
現代はオンライン学習や動画教材が急速に発展していますが、
もし全てがオンラインになってしまったら、失われる経験は少なくないはずです。
その最たるものが、**「ケンカと仲直り」**だと為末さんは言います。
これは人として生きていくうえで、欠かせない経験です。
すべては「遊び」から始まる

子どもが時間を忘れて夢中で遊んでいる姿は、
アスリートが試合中に“ZONE”に入っている状態と似ています。
すべては「遊び」から始まる。
これは、子どもの熟達を願う大人として、ぜひ知っておきたい知識です。



