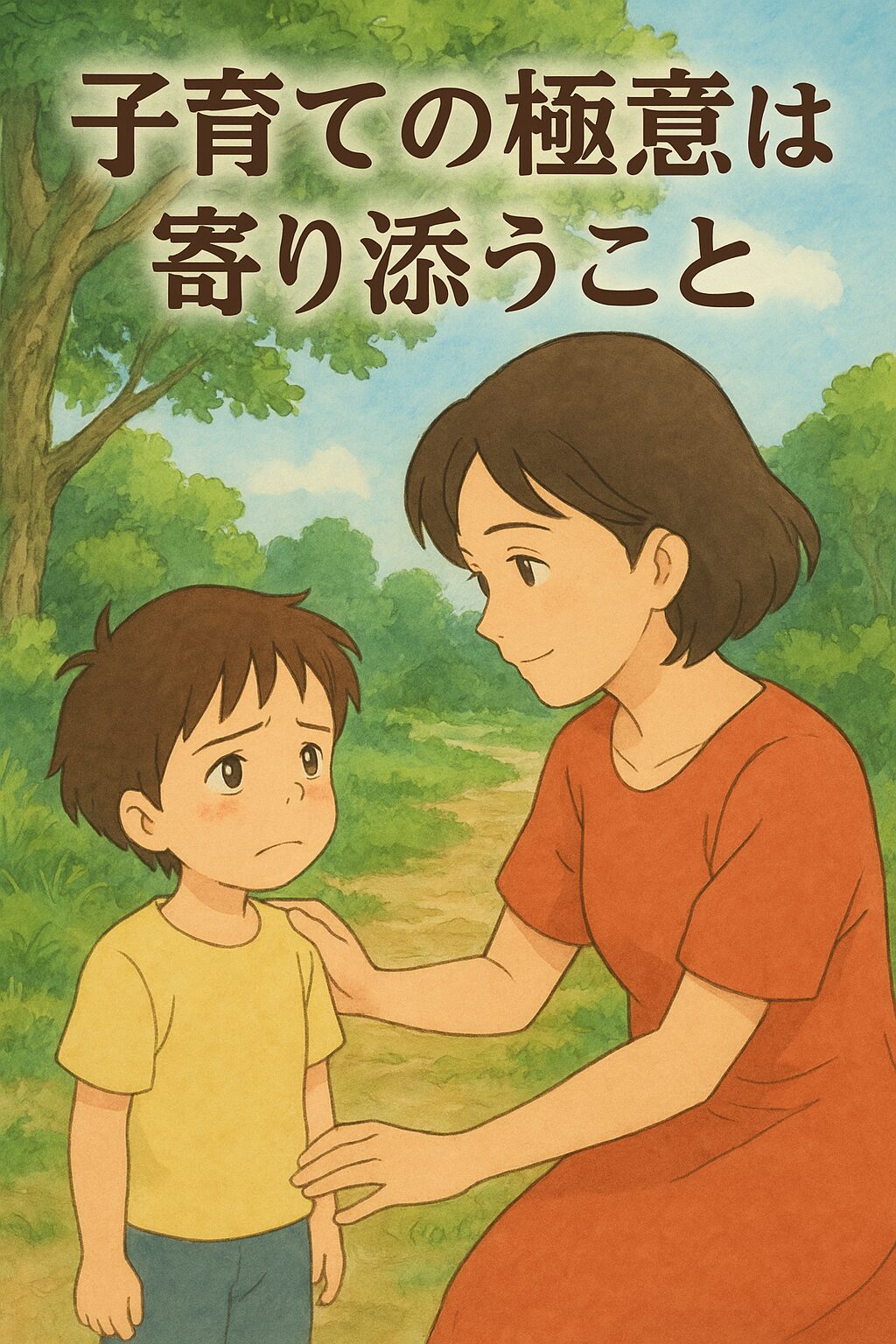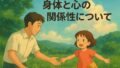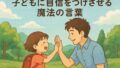子どもに寄り添っていますか?
当たり前のようでいて、忘れがちなこのこと。
寄り添うことを忘れたとき、子どもはプレッシャーを抱え、小さな心に大きな不安を背負ってしまうことがあります。
この記事では、そんな時に思い出したい「子育ての極意」をお伝えします💡
よかれと思った指導の落とし穴
全国各地の園や学校、スポーツクラブなどで指導をさせていただくようになってから、
20年以上の月日が経過しました。
今は年間で1万人以上の子どもたちと出会う機会に恵まれています。
その中で、教員や指導者の方々からは、
「よかれと思って指導していたことが、実は逆効果だったと気がつきました」
という声をよく耳にします👂
涙ながらの問いかけから学んだこと

先日、都内のある小学校で1年生の体育の授業を行いました。
授業の冒頭で、
「このトレーニングをすると、走るのが速くなるし、ボールを投げたり蹴ったりするのも上手になるよ!」
と伝えると、子どもたちはとても集中して取り組み、楽しく有意義な時間になりました。
授業の終わり、挨拶をした直後に、一人の女の子が瞳に涙を浮かべ、
消え入りそうな声でこう言いました。
「本当に投げられるようになるの?😢」
話を聞くと、その子はボールを投げるのがとても苦手で、不安を抱えていたのです。
私はその子に、
- 誰にでも可能性があること
- 早くできることだけが大切なのではないこと
- 身体を上手に使うトレーニングを続ければ必ずできるようになること
を伝えました。
するとその子は、私の目を見て納得したように小さく頷き、教室に戻っていきました。
その後ろ姿を見送りながら、
小学校に入学して間もない1年生の子が、なぜあんなに思い詰めてしまうのだろう…
と考えさせられました。
現代社会には、子どもに強いプレッシャーを与えてしまう要素が数多く潜んでいるのかもしれません。
クラスの雰囲気を決めるのは「寄り添い」
全国で授業を行っていると、雰囲気の良いクラスにも、荒れているクラスにも出会います。
その違いを生む大きな要因は、先生と子どもの関わり方です。
先生が子どもに寄り添えていないクラスでは、
「よかれと思った指導」が逆効果になる場面が多く見られます。
親として忘れがちな視点

これまで
「子ども目線と大人目線」
「能動的な子ども・受動的にさせる大人」
「子ども側の事情と大人側の都合」
といった表現で考えていましたが、少し曖昧でした☹️
そんな時、幼児教育に携わる大学の先生が、ある会議でこう言いました。
「その違いは、子どもに寄り添った教育をしているかどうか、ですね」
この言葉で一気に整理されました!
確かに、雰囲気の良いクラスの先生は、常に子どもの側に立ち、寄り添った教育を実践しているのです。
私自身、我が子に対しては大人目線になりがちで、
寄り添う気持ちを忘れてしまうことがあります💦
特に忙しい時や急いでいる時、大人の都合で子どもを動かそうとしてしまいます。
しかし、スピードが加速する現代だからこそ、時には深呼吸をして立ち止まることも必要です。
時間的な余裕は心のゆとりにつながり、子どもに寄り添うことを思い出させてくれます。
子どもを信じ、見守るということ
“よかれと思って”子どもに余計な指導をしてしまうことは、
まだ準備が整っていない雛を、無理に巣立たせようとするようなものかもしれません🐣
子育ての極意とは、子どもが自ら育つ力を信じ、見守り、育んでいくこと。
「ゆっくり熟成して、やがて自ら羽ばたいていけるように」
そんな想いを胸に、子どもたちと関わっていきたいと思います。
あなたは今日、子どものどんな瞬間に寄り添えそうですか?