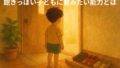創造とは、特別な才能ではなく「世界を新しく見直す姿勢」です。
感じ、考え、理解したものを組み合わせて、自分なりの表現をすることです。
創造性は、感受性・理性・知性が重なり合うところに生まれます。
ただ新しいものを作るのではなく、今ここにあるものを新たに見直す力。
それは人間が持っている最も素晴らしい能力です🧠
感じ、整え、理解し、創り出す——。
今回は指導者の創造性を育む方法について説明します。
科学を学び共に創る
どのように指導を組み立て、どのような考えでその時間や空間を創り上げていくか――。
それは、運動指導における大きな醍醐味です✨
まず、科学的な知見を持って指導にあたることが大切です。
なぜこの運動をするのか、それがどんなことにつながるのか、
など運動の目的やねらいを科学的に説明できれば、子どもの興味はぐっと深まります。
そして、子どもたちと共に愉しみながらステージ(舞台)を創るという意識を持ちましょう。
時には、
指導者自身が童心を忘れずに子どもたちの世界に分け入ることも必要です👦
そのために、以下のような知識や視点を持って運動指導にあたると、
その意味がいっそう深まります。
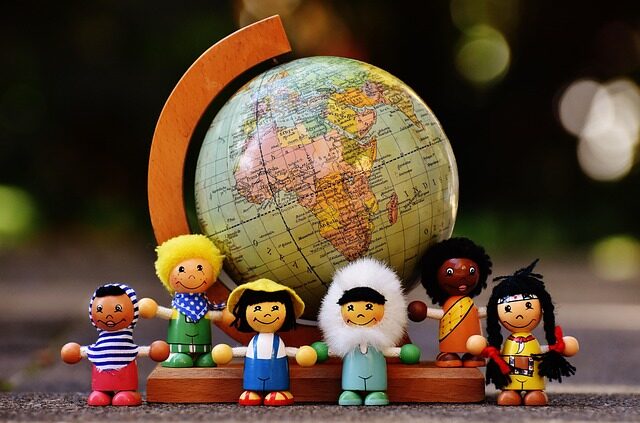
1.様々な感覚刺激を使う
例えば、合図で反応する場面では、
以下のように、視覚、聴覚、触覚など、複数の感覚を意識して使いましょう🧠
✅「先生が立ったら真似をして立ちましょう」(視覚)
✅「笛が鳴ったら素早く立ちましょう」(聴覚)
✅「目を閉じて床の振動を感じたらすぐに立ちましょう」(触覚)
また、
「笛が一回鳴った時は立たず、二回鳴った時に立つ」
というように、単純反応から弁別反応に変えることで、刺激がより豊かになります。
2.課題設定を変える
課題を与える際は、単なる“運動の課題”を“目的のある課題”に変えてみましょう。
①スキップをさせる場面で、
「ケンケンを二回ずつしてみよう」
という運動の課題を目的のある課題に変える例。
✅「タタン、タタンという音をつくってみよう」
✅「前に出した掌を膝でジャンプキックしながら進もう」
このように目的のある課題にすることでスムーズにできるようになる子が増えます✨
②ケンケンで移動するという運動の課題を目的のある課題に変える例。
✅「丸いホースを脚にかけて運ぼう」
✅「膝の上に置いた縄を落とさないように片足で進もう」
このように目的のある課題に変えることで、
バランスをとって移動できる子がたくさん出てきます👦

3.身についた動きを使う
運動の発達段階に応じて、使う動きを選びましょう。
課題の難易度と動きの複雑さのバランスが重要です✅
基本的にはすでに身についている動きを使うことで、
子どもは運動の課題に集中しやすくなります👧
例えば三歳の幼児に、
指導者の動きを模倣して一緒に移動し、
同時に止まるという運動を行う場合、
「サイドステップで移動して止まる」
⬇️
「前に歩いて止まる」
方が適しています💡
また、リングをステップする場合も、
「スキップ」
⬇️
「走る」や「両足ジャンプ」
の方が効果的です✨
もし子どもたちが与えられた課題を全くこなすことができないような場合は、
動きが難しいと考え、
使う動きをより単純なものに変えてみましょう✅
4.知的好奇心を与える
指導者の言葉に従うだけでなく、
子どもが知的好奇心をくすぐられ、創造性を発揮できるような時間をつくりましょう。
フラフープを潜り抜ける運動を行う際の例。
「レベル1:潜り抜ける」
「レベル2:潜ってからキャッチ」
「レベル3:ペアで考えてみよう!」
このように、段階をつけると、
子どもは夢中になってアイデアを出し、工夫を始めます😊
また、鬼ごっこ終了時に、
「逃げ方や捕まえ方を工夫した人はいますか?」
と聞いて、
考えたり創造したりしたことを発表させる時間を設けると、
子どもたちから様々な意見が出てきます👧
そんな友達の発想をヒントにしながら、動きが変化していく過程こそ創造性の育ちです🌱
また、知的好奇心を刺激する発問、Q&Aも効果的です。
Q.「足は近くについた方がいいかな?遠くかな?」
A.「この動きは円運動だから、近い方が半径が短くなってコンパクトに回れるね」
指導者の創造性を発揮したこうしたやりとりが、
子どもの知的好奇心を刺激し、理解を深め、思考を広げます🧠

5.運動欲求に応じて刺激を変える
子どもの行動や態度から、今どんな運動欲求があるのかを観察しましょう。
広い場所に来た途端に
・大声を出して走り出す子
・ボールで遊びたがる子
・並んだ時に動き続ける子
など子どもが運動欲求を発散する姿を見ることがあります。
そのような子どもの動きや態度に応じて、
運動の刺激を変える意識を持ちましょう。
✅大声を出して走り出す
「しばらく雨が続いていたから、声を出して走ってエネルギーを発散したいのだな」
✅ボールで遊びたがる
「地味な動きが続いたから、用具を操作するような運動刺激を求めているのだな」
✅並んだ時に動き続ける
「運動会の行進練習が多い時期だから、並ぶことにストレスが溜まっているな」
このようにサインを読み取り、
求めている運動刺激を与えて運動欲求を満たしてやることで、
子どもの行動は落ち着いていきます😊

6.物を渡したら自由に操作させる
子どもにボールを渡すと、
そのままじっと持っている子は少なく、
多くの子が弾ませたり、投げ上げたりして遊び始めます👦
そのような時、しばらく自由にさせてみましょう✨
これは、用具を操作することによって、
その物を自分の身体の一部のように感じられる「身体化」を促すことになります。
また、自由に操作している間に脳に刺激が入り
運動欲求の発散にもつながります🧠
「まだ何も言ってない」
「勝手にやらない」
と言いたくなる場面でも、
“身体化を促している”
”運動欲求を発散させている”
時間だと知れば、
指導の仕方や言葉かけが変わるでしょう😊
7.コミュニケーションを介する
指導開始直後、集団全体が少し硬い空気に包まれていることがあります💦
出会って間もない集団や、普段と異なる合同授業などでは特にそうです。
そんな時は、仲間と関わる運動を取り入れ、
コミュニケーションを介するような展開にしましょう👭
✅ペアでのストレッチ
✅リズムを合わせて移動する運動
✅ボールを使った共同操作の運動
などが効果的です✨
コミュニケーションが生まれることで、場の空気が自然にやわらぎます😊
まとめ
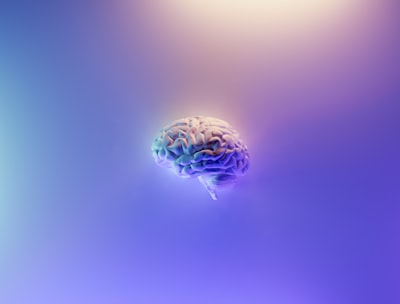
創造性とは、特別な才能ではなく、
人が持つ「新しい価値を生み出そうとする力」です✨
創造的であるとは、
これまでの知識や経験をもとに、
新しい組み合わせや視点を見つけ出すことです🧠
それは運動やスポーツに限らず、
日常の問題解決や人との関わり方にも発揮されます。
創造性を高めるためには、
感受性・理性・知性がそれぞれ協調して働くことが重要です。
創造性とは、行動につなげる総合的な力です。