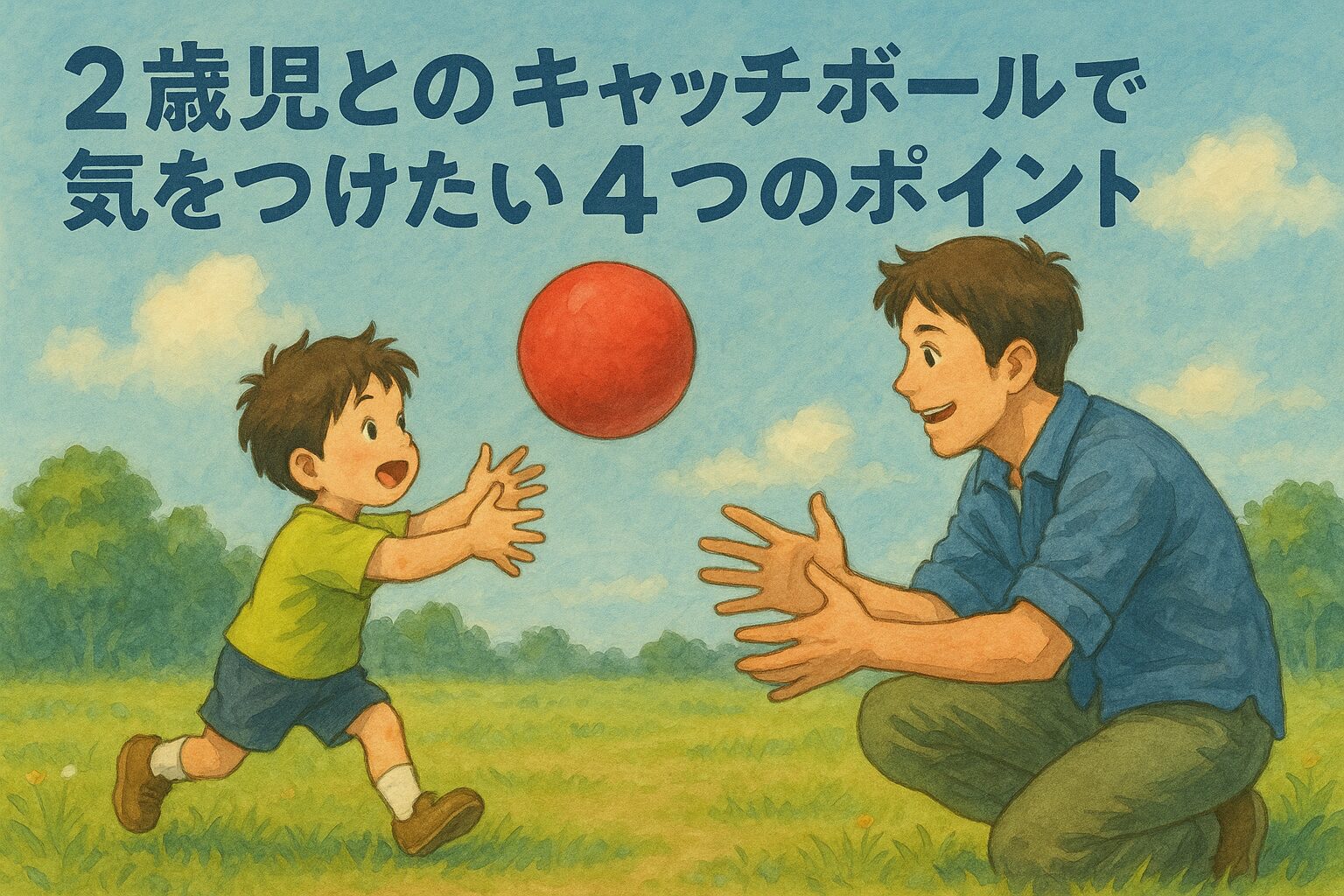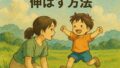2歳の子どもとキャッチボールをしてみたけど、なかなかボールをキャッチできない…。
そんな悩みを持つ親御さんに向けて、
運動発達の観点から大切な4つのポイントをご紹介します。
発達に合った関わり方を知れば、キャッチボールはきっともっと楽しくなるはず。
先生からの質問がきっかけでした
先日、運動指導の方法に関するお仕事で、小学校の先生方向けに研修を行わせていただきました。
その中で、子育て中の若い男性の先生から、こんな質問をいただきました。
「2歳の息子がなかなかボールをキャッチできません。うまくボールを捕れるようにするにはどうしたらいいでしょうか?」
その先生は学生時代に野球をされていたそうで、「ボールは捕れるのが当然」という感覚だったようです。
でも、実は2歳の子にとって「ボールをキャッチする」というのは、なかなか高度な運動。
そこで私がアドバイスした、キャッチボールがうまくなる4つの方法をご紹介します。
✅ キャッチボールが上手になる4つのポイント

目線より高く投げない
子どもは、ボールが飛んでくるのを「見て認知し、身体で反応してキャッチする」という流れで動いています。
しかし幼い子は、運動発達の関係で目線より高い位置にあるボールをうまく認知するのが難しいのです。
ですから、ボールは顔の高さより上げずに渡すような感じで投げてあげましょう。
胸でキャッチさせ、その感覚を覚えさせる
「キャッチって、どういうこと?」
それを伝えるには、胸に当たった感覚を教えてあげるのが有効です。
親がボールを手に持ち、2〜3回軽くお子さんの胸にポンポンと当ててみましょう。
そして、こんな声かけをします:
「これがポン!ってきたら、ギュッと抱っこするように捕まえてごらん」
言葉と感覚を結びつけることで、理解が深まります。

投げる動作は“大きく・ゆっくり”
両手で下投げするように、大きく、ゆっくり見せるように投げてあげましょう。
軌道がはっきり見えることで、子どもも予測しやすくなります。
運動は「ゆっくりできないものは、速くしてもできません」。
思っている10倍くらいゆっくり動くのが、ちょうどいいスピードです。
近くから始め、少しずつ距離を遠くする
まずは手が届くくらいの距離から始めて、徐々に距離を伸ばしていきましょう。
「手が届く距離」と「届かない距離」では、脳の情報処理の仕方が異なるといわれています。
子どもの発達に合わせて、“近くから遠くへ”が原則です。
実際にアドバイスしてみたら…
その先生は「家に帰って早速やってみます!」と嬉しそうにおっしゃっていました(笑)
さて、うまくいったでしょうか。
🌱 おわりに

子どもの運動発達には順序性があります。
焦ってその順番を飛ばそうとせず、おおらかに見守ることが何より大切です。
その子が今、求めている“ちょうどよい刺激”を与えてあげられたら、自然と運動能力は育っていきます。