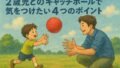「運動ができる子と、そうでない子の違いって何だろう?」
子どもの運動能力は、生まれつきの才能だけで決まるものではありません。
実は、“ある力”を育むことで、誰でもぐんと伸ばすことができるのです。
キーワードは「運動の学習能力」。
本記事では、幼児期から児童期にかけての発達特性や子どもの主体性を大切にした関わり方をもとに、
無理なく・自然に運動能力を高めるヒントをお伝えします。
「先回りしないこと」こそ、
子どもの潜在能力を引き出す最大のカギだった——。
そんな気づきが得られる内容です。
親として、指導者として、ぜひ読んでいただきたいお話です。
運動がすぐできる子が高い「運動の学習能力」とは

「運動がすぐにできるようになる子と、
なかなかできるようにならない子がいるのはなぜだろう?」
子育てをしている親ならば、一度は考えたことがあるのではないでしょうか?
私もずっとそんな疑問を抱きながら、子どもへの運動指導に携わり、
そして自らも子育てをしてきました。
そんな中で行き着いたキーワードが、
「運動の学習能力」です。
運動がすぐにできるようになる子は、
この運動の学習能力が高いのです!
運動の学習能力はどう育てる?
では、その運動の学習能力はどうしたら高めることができるのでしょうか?
答えは・・・「何もしないこと」です!
「いやいや、さすがにそれはないでしょ!」
そんな声が聞こえて来そうですね(笑)
別の言い方をすると、
「先回りをしないこと」です。
運動能力を高めるための習い事が当たり前の現代社会

現代は、昔に比べ子どもの習い事がとても充実しています。
スポーツ、音楽、学習系など、幼い時期から何でも始められます。
中には、生まれた直後からの習い事すらあるほどです。
「早く何かさせないと手遅れになっちゃうかも」
「小さいうちからいろいろ身につけさせてあげたい」
親として、そんなふうに焦る気持ちもよく分かります。
でも、そんな時こそ、深呼吸をして一旦落ち着きましょう(笑)
子どもはその時に必要な刺激を求めている
子どもは、成長していく過程で、
その時々に必要な感覚や運動の刺激を自ら求めています。
乳児期

赤ちゃんが何でも口に入れるのは、
舌の感覚を使って物の特徴を把握しようとしているから。
また、離乳食を床に落とすのは、
「投げる」という運動を試したいからなのです。
ちなみに我が家では、毎回新聞紙を床に敷いて、いつ投げられてもいいようにしていました(笑)
片付けのストレスが減るので、おおらかに接したい方におすすめです!
幼児期

砂遊びや水遊びを通じて、
砂のザラザラ感や重さ、水の冷たさや流れの感覚など、
さまざまな刺激を楽しんでいます。
広い場所に行くと、ずーっと走っているのも、
脳と身体に必要な刺激を自ら取りに行っている証拠です。
大人になった今の私は、真似できません(笑)
今の私には、その刺激は必要ないのです・・・。
児童期

自分が小学生だった頃、どんな遊びが楽しかったか思い出してみてください。
鬼ごっこ、ドッジボール、縄跳びなど・・・。
何かの運動に熱中した経験があるのではないでしょうか?
それこそが、その時期の脳と身体が求めていた刺激です。
さらに高学年になると、難しいルールの理解が進み、
野球、サッカー、バスケやバレーなどのスポーツを好む子も増えていきます。
運動能力を高めるために大切なのは「主体性」
このように、子どもは成長に応じて、
その時の発達に必要な運動や感覚の刺激を自ら求め、学んでいく存在です。
適切な時期に、適切な刺激を受ける経験を重ねる中で、
運動の学習能力は自然と高まっていきます。
先回りせず、待ってみる
とはいえ、先回りしたくなる気持ちもよく分かります。
私も子どもと関わる中で、あれこれと考えては、
「よかれ」と思って手を出しすぎたことが多々ありました。
でも今思うのは、子どもの主体性を育むには、”待つこと”が大切だということ。
主体的に動くことで、脳は育つ
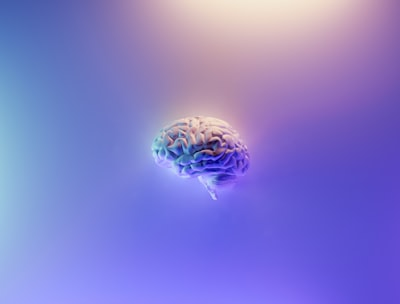
主体的な行動が、脳を育てる——これは科学的にも言われていることです。
人間は「やらされている」とき、脳があまり働きません。
子どもの頃、親に「勉強しなさい」と言われて、
「今やろうと思ってたのに!」とやる気をなくした経験、ありませんか?(笑)
遊びの中に育ちがある
一見ムダに思えるような子どもの遊びの中には、
主体性・創造性・運動と感覚の刺激がぎっしり詰まっています。
自ら考え、動き、感じることで、
子どもの脳と心と身体は、バランスよく育っていくのです。
子どもが自ら成長するのを信じて、見守るという選択

「早くから何かさせないと手遅れになるかも」——そんな焦りは手放して大丈夫。
同じ時間は二度とない、かけがえのない子育ての時間です。
子どもの心の動きも観てみましょう。
心にゆとりを持って、
子どもが自ら健やかに成長していく姿を、信じて見守りましょう。
✅ポイントまとめ
- 子どもの運動能力は「運動の学習能力」によって伸ばせる
- その力は、主体的な遊びや経験の中で自然と育つ
- 親や指導者は「先回りせず、信じて待つ」姿勢が大切